地震や台風など、災害はある日突然やってきます。非常食やラジオなど本格的な防災グッズがあれば安心ですが、現実には「まだ何も揃えてない…」という方も多いのではないでしょうか。
筆者自身、東日本大震災で短期間の断水を経験しました。そのとき痛感したのが、「特別な道具がなくても、家にあるものを“工夫して使う”だけで、意外と乗り越えられる」ということです。
この記事では、実際の震災時に役立ったり、「あのときこうしておけばよかった…」と感じた経験、そして被害の大きかった地域に住む知人から教えてもらった知恵をもとに、“家にあるものでできる防災アイデア”をご紹介します。
ラップは「食器の衛生管理」に大活躍

断水したとき、予想以上に困ったのが「食器が洗えない」という問題でした。料理はできても、洗い物ができない。スプーンや皿を一度使うと、それっきり。限られた水を手洗いに使うのか、食器に使うのか――そんな判断を迫られる毎日でした。
そこで活躍したのが、食品保存用のラップ。お皿やボウルの上にラップをぴったり敷いてから料理を盛りつければ、食後はラップを外して捨てるだけ。水を一滴も使わずに、再びその皿が使えるのです。
特に子どもがいる家庭では食器の回転率が高くなりますし、衛生面でも大きな安心感がありました。ちなみに、使い捨ての紙皿よりもラップの方が収納スペースも少なく済み、コスト面でも優秀です。
「あってよかった」と心から思えたアイテムのひとつです。
ポリ袋は「水タンク」として大活躍

震災直後に一番困ったのが、水の確保でした。数日間の断水で、水道からは一滴も出てこない。給水車は来てくれるけれど、配られるのは限られた量。持参した容器に水を入れてもらう方式だったため、容器が足りない家庭は非常に苦労していました。
我が家で活躍したのは、大きめのポリ袋。具体的には、45Lのゴミ袋を2重にしてバケツの中にセットし、そこに給水された水を注ぎました。袋だけで持ち歩くのは不安でしたが、バケツや段ボールなどに袋を入れて支えることで、しっかりと水を運ぶことができたのです。
しかも、ポリ袋は密閉性が高く、しっかり口を縛れば清潔な状態で一時保管も可能。洗面所に置いて、手洗い用にしたり、調理用の水として分けたりと、状況に応じて柔軟に活用できました。
非常時には「水の置き場所」「持ち運び」「衛生管理」の3点がすべて課題になりますが、ポリ袋ひとつでそれらをカバーできたのは本当に助かりました。
新聞紙は「スリッパ」と「防寒」に

寒さに震える避難生活のなかで、地味に体力を奪われるのが「床の冷たさ」です。特に体育館などの避難所では、床がコンクリートや木製であることが多く、底冷えが長時間続くと、身体の芯まで冷え切ってしまいます。
そんなとき、助けられたのが新聞紙。敷いたり巻いたりするだけで、しっかりと体を保温してくれました。特に役立ったのが「即席スリッパ」です。新聞紙を何枚か重ねて足裏の形に折り、ガムテープでとめるだけで、簡単なスリッパが完成。床の冷たさが軽減され、精神的にもほっとしたのを覚えています。
また、肩にかけてケープのように使ったり、寝るときに身体に巻いたりと、寒さ対策の即席アイテムとして万能でした。
さらに、湿気を吸いやすいため靴や衣類の中に入れておけば乾燥材代わりにもなりますし、着火剤としても使用できます。まさに“災害時のマルチプレイヤー”。
ゴミ袋は「即席レインコート」に

災害時、思いがけず外に出なければならない場面があります。たとえば、給水所に並ぶ、近所の安否確認に行く、ごみを出すなど――。そんなときに困るのが「雨」です。
我が家で重宝したのが、45リットルの大きめゴミ袋。底に十字にハサミを入れて頭を通す穴を作り、両脇に腕が出るような切れ目を入れれば、簡単なポンチョ型のレインコートになります。
素材が薄いので本格的な雨具には劣りますが、短時間の移動には十分です。何よりも、衣服を濡らさずに済むことで、着替えの節約にもなりました。
災害時の着替えは限られているうえ、洗濯も困難なので「濡れないこと」はとても重要なのです。
ウェットティッシュは「手洗いの代わり」に

断水中の生活で、私がもっともストレスを感じたのは「手を洗えないこと」でした。料理や食事の前、トイレのあと――当たり前にしていた手洗いができないだけで、衛生面への不安が一気に高まります。
このとき、本当に救われたのがウェットティッシュでした。水が使えない状況でも手を拭える安心感は想像以上で、「これがなかったら…」と思う場面が何度もありました。
災害時は、体調を崩すと医療機関へのアクセスも難しくなるため、清潔を保つことが何よりの“予防”になります。
また、顔や体を拭く、テーブルを拭くなど、汎用性が高いのも利点です。乾きやすいので封をしっかり閉める必要がありますが、普段から少し多めにストックしておくだけで、非常時に「買っておいてよかった」と思えるアイテムになります。
使い捨てカイロは「夜の防寒」と「スマホ保温」に

停電と断水が続く夜。冷え込みの厳しい3月だったこともあり、電気毛布もストーブも使えず、寒さがじわじわと体力を奪っていきました。
そんなとき、布団の中でそっと温もりをくれたのが、使い捨てカイロでした。お腹や背中に貼るだけで体感温度が大きく変わり、精神的にもほっとできます。
さらに、意外な用途だったのが「スマホのバッテリー保護」。震災当時、気温が低かったせいかスマートフォンの電池残量が突然ゼロになり、情報収集に支障が出たのです。
スマホとカイロを一緒にタオルに包んで保温することで、電池の減り方が明らかに穏やかになりました。
ペットボトル+スマホライトで「簡易ランタン」

停電直後は、家族の顔すら見えないほどの暗さに戸惑いました。そんな中、スマホのライトに、水を入れたペットボトルを重ねただけで、部屋全体がふんわりと明るくなったのです。
光が水に反射して拡散され、まるで小さなランタンのよう。テーブルの中央に置けば、ちょっとした団らんの明かりにもなりますし、手元を照らすには十分な光量があります。
透明のペットボトルならどれでも使えますが、500ml以上の少し大きめサイズが安定感もあっておすすめです。
まとめ:「ないと困る」より「あるもので備える」

災害時にもっとも大切なのは、「完璧な備え」ではなく「柔軟な工夫」です。今回ご紹介した7つのアイテムは、いずれも特別な防災グッズではありません。
筆者自身は幸いにも、短期間の断水を経験した程度で済みました。しかし、被害が大きかった地域に住む友人たちから聞いた実体験には、想像を超える現実がありました。そこで役立ったのが、今回ご紹介したような“代用品”だったのです。
たとえ本格的な防災グッズを揃えていなくても、身の回りのものを工夫して使うだけで、できることは意外と多い――そのことを、彼らの声から学びました。
完璧じゃなくていい。まずはひとつ、「これは使えるかも」と思えるものを見つけることから始めてみませんか。
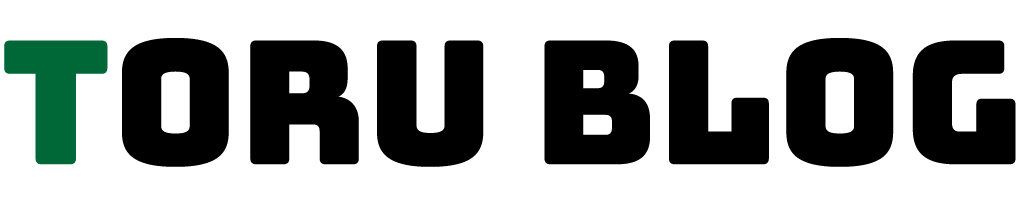



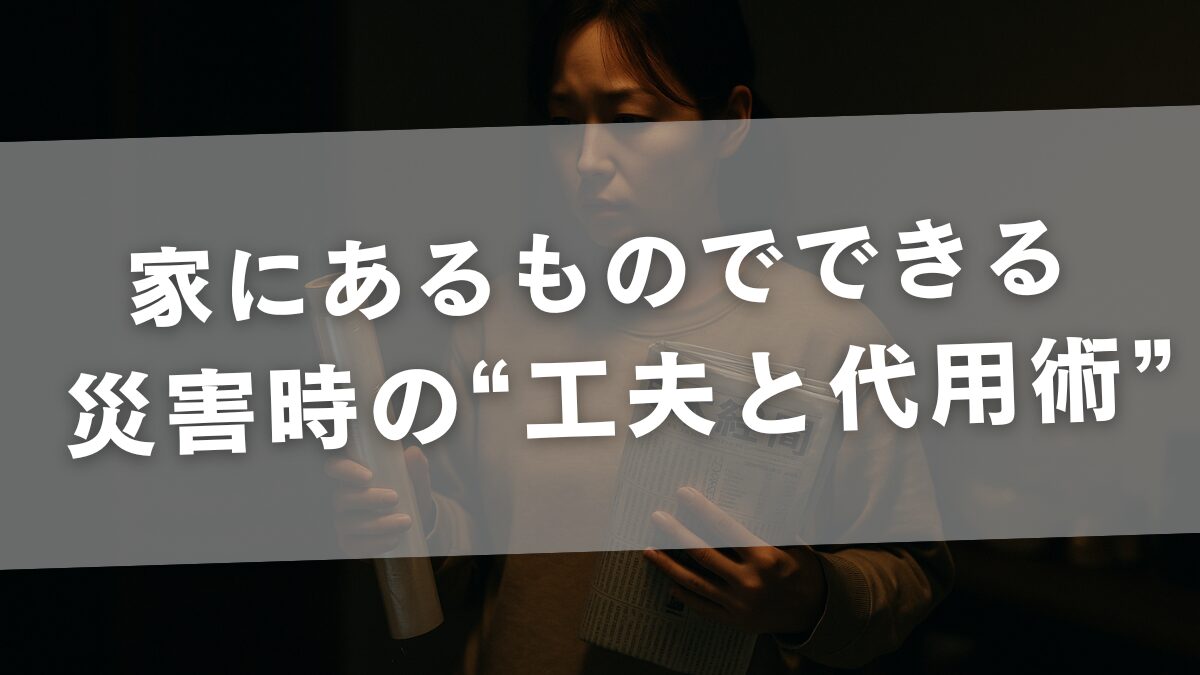
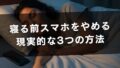
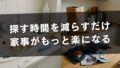
コメント