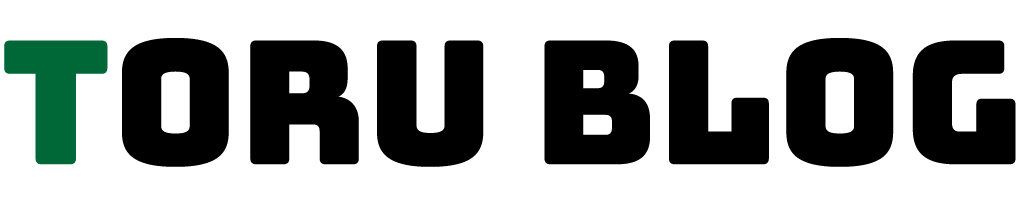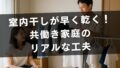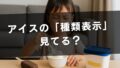スマホの充電が切れそうなときに限って、近くにコンセントが見つからない──。そんな小さなストレスを、忙しい家庭の中で何度も感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
特に共働きや子育て中の家庭では、日々の生活動線が複雑になりやすく、決まった充電場所だけでは対応しきれない場面が出てきます。そこで今回は、「家の中どこでもスマホを充電できる環境」をつくるための工夫を紹介します。配線の悩みを軽減し、家事や育児中でもスマホが常に使える快適な環境づくりを目指します。
なぜ“どこでも充電”が必要なのか?

スマホは現代の生活に欠かせない道具ですが、充電のタイミングや場所に関するストレスは意外と見過ごされがちです。とくに共働き家庭や子育て世帯では、家族全員がスマホやタブレットを使う時間が増え、限られたコンセントを奪い合う状況が発生しやすくなります。
たとえば、料理中にレシピ動画を見ようと思ったら、キッチンに充電スポットがなくて断念したり、寝室でスマホを操作しているうちにバッテリーが切れて、わざわざリビングまで取りに行く──そんな些細な不便が日常に溶け込んでいるのです。
また、子どもが動画を見ている最中に充電が切れてぐずってしまう、家族の誰かが延長コードごと持ち出して充電できなくなった、という場面も決して珍しくありません。
このように「充電ができる場所が限られている」ことは、思った以上に生活ストレスの要因となっています。だからこそ、あらかじめ“充電できる場所”を複数用意し、どこにいてもスマホを使える環境を整えておくことが、忙しい家庭ほど大きな助けになるのです。
実際にやってみた充電スポットの増設方法
まず「家の中の使いたい場所」を洗い出す

はじめに行ったのは、「スマホをどこでよく使っているか」を把握することでした。なんとなく不便と感じていても、実際にスマホを操作する場所は家族ごとに異なります。リビングのソファ、寝室のベッド横、ダイニングテーブル、洗面所横など──意外な場所での使用頻度に気づけることもあります。
家族の動線や滞在時間が長い場所を可視化すると、「ここにもあったら便利だな」という充電スポットの候補が自然と見えてきました。
延長ケーブル+USBポート付きタップを活用
次に取り入れたのは、USBポート付きの電源タップと延長ケーブルの組み合わせです。リビングではテレビ裏の電源に差し込んだ延長コードを、サイドテーブルの裏に這わせることで見た目もスッキリ。コードが床に散らばることなく、安全性も確保できます。
また、USBポートが複数あるタップを選べば、スマホ以外にもタブレットやワイヤレスイヤホンなどを同時に充電可能。家族で取り合いにならないのもポイントです。
コードを目立たせたくない場所では、マスキングテープやコードクリップを活用。壁や家具の背面に沿わせて固定すると、インテリアの邪魔にならず、掃除の際もストレスが減ります。
モバイルバッテリーを“定位置”で使う発想

持ち歩くものという印象が強いモバイルバッテリーですが、あえて「定位置で据え置き」で使う方法も取り入れました。リビングの棚や子どもの学習スペースに設置することで、電源が遠い場所でも手軽に充電が可能になります。
たとえば、リビングで子どもがタブレットで動画を見るとき、コンセントが届かずに困ることがよくあります。そんなとき、棚に置いてあるバッテリーに繋げるだけで済むようにしておけば、親も子もストレスなく過ごせます。
バッテリー自体の充電は、夜にまとめて一か所で行うようルーティン化すれば、持ち出し忘れも防げます。デザイン性の高いバッテリーを選べば、インテリアとの相性も◎。
「ここにあれば使いやすいという観点は収納と共通しています」毎日使う日用品の「定位置」収納アイデア
使ってみてわかったメリットと注意点
メリット
充電スポットを家中に分散させたことで、まず大きく感じたのは「場所の取り合い」がなくなったことです。以前はリビングの一か所に家族全員がスマホを持ち寄っていたため、コードが絡まり、誰かがタップを抜いてしまうといったトラブルも日常茶飯事でした。
今は各自が自分の“定位置”で充電できるようになったため、無駄な移動が減り、家事や育児の合間にサッとスマホ操作ができる快適さを実感しています。たとえば、キッチンでレシピを確認しながら料理をしたり、脱衣所で子どもの動画を見せながら支度を整えたり──これまで「充電できないからやめていた行動」が当たり前にできるようになりました。
また、来客時に「充電器ありますか?」と聞かれた際にも、さりげなく「こちらでどうぞ」と案内できるようになり、暮らしのスマートさがひとつ上がった感覚もあります。
注意点
一方で、配線や設置の際に注意したい点もあります。まず気をつけたいのは“見た目の雑多感”です。電源タップやケーブルが目に付く場所に無造作に置かれていると、せっかくの生活空間が乱雑に見えてしまいます。コード収納ボックスや壁面設置、家具裏の固定など、目立たせない工夫が必要です。
また、小さな子どもがいる家庭では、安全面にも配慮が必要です。タップや延長コードが手の届く位置にあると、引っ張ってしまったり、口に入れてしまう危険も。高めの位置に設置したり、コードカバーを使用するなどの対策をとるようにしましょう。
さらに、安価な充電タップやノーブランドのモバイルバッテリーを使用する場合は、発熱や過電流のリスクもあります。PSEマークの有無や通電時の発熱具合を確認し、万が一に備えて火のそばには設置しないなどの基本的な安全管理を忘れないようにしましょう。
まとめ|充電ストレスを減らす「一手間」のすすめ

スマホの充電場所を複数用意するという工夫は、決して大がかりなことではありません。しかし実際に取り入れてみると、家族の動きがスムーズになり、暮らしの小さなストレスが確実に減っていくのを感じました。
「ここでも充電できたらいいのに」と感じた瞬間があれば、そこが設置候補です。まずはリビングや寝室など、自分や家族が長く過ごす場所から始めてみると、無理なく日常に取り入れられます。
重要なのは、使いやすさと見た目の両立、そして安全性の確保です。延長コードやタップに頼るだけでなく、収納や配線の工夫、子どもの手の届かない配置などを意識することで、より快適な環境に整えることができます。
毎日当たり前のように使うスマホだからこそ、充電のしやすさは暮らしの快適さに直結します。「どこにいても充電できる家」は、家族全員がストレスなく過ごせる“見えない安心”を支える大切な要素。少しの工夫から、ぜひ始めてみてください。